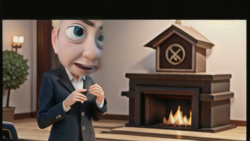墓石
墓石 宝篋印塔:先祖供養と子孫繁栄の象徴
宝篋印塔とは、主に供養塔や墓碑塔として用いられる仏塔の一種です。その名前は、お経を納めた宝篋(ほうきょう)と呼ばれる入れ物を安置することから由来しています。この入れ物には、陀羅尼経と呼ばれるお経が納められており、功徳があるとされています。宝篋印塔の歴史は古く、中国から伝わったとされています。日本では、奈良時代から鎌倉時代にかけて広く建立され、様々な祈願を込めて建てられました。例えば、死者の供養はもちろんのこと、五穀豊穣や無病息災、子孫繁栄など、人々の願いが込められていました。宝篋印塔は、一見すると複雑な構造をしていますが、上から順に相輪、伏鉢、請花、塔身、基礎と、それぞれに意味があります。相輪は、空を象徴し、宇宙を表しています。伏鉢は、煩悩を覆い隠すという意味を持ち、請花は、仏様への供え物を表します。塔身には、前述の宝篋が納められており、基礎は、大地を表し、安定を象徴しています。このように、宝篋印塔の各部分は仏教思想に基づいて設計されており、深い意味が込められているのです。現代では、個人のお墓として宝篋印塔を用いるケースも少なくありません。特に、代々続く旧家や、詳細な過去帳が残る名家、寺院の歴代住職の墓など、歴史と伝統を重んじる家において、宝篋印塔は選ばれています。その荘厳な姿は、先祖への敬意と子孫の繁栄を願う気持ちの表れと言えるでしょう。また、宝篋印塔は、単なる墓石ではなく、一族の歴史と伝統を後世に伝える大切な役割を担っているとも言えます。