葬儀と法事における賽銭

葬式を知りたい
先生、葬式や法事でお金を包むとき、『賽銭』って言葉を使いますか?なんとなく神社で使う言葉のような気がするのですが…

お葬式専門家
いい質問ですね。賽銭は、神様へのお供え物として神社で使われる言葉です。お葬式や法事でお金を包む場合は『御仏前』、『御香典』、『御霊前』などを使います。これらは仏様へのお供え物という意味です。

葬式を知りたい
なるほど。『御仏前』、『御香典』、『御霊前』ですね。これらは全部、仏様へのお供えという意味で、葬式や法事で使う言葉なのですね。

お葬式専門家
その理解で大丈夫です。状況によって使い分けるので、また別の機会にそれぞれの違いを説明しましょう。
賽銭とは。
お葬式やお法事に関する言葉で「賽銭」というものがありますが、これは本来、神社などで神様に差し上げるお金のことです。お寺や仏像にお供えする場合もありますが、本来の意味とは少し違います。
賽銭の意味

賽銭とは、神仏への感謝の気持ちや願いを込めてお供えする金銭のことです。古くは米や野菜などの農作物をお供えしていましたが、時代の流れとともに貨幣経済が発展し、金銭をお供えするようになりました。葬儀や法事では、故人の霊の安らかな成仏を願う気持ちを表すために賽銭をお供えします。
金額については、特に決まりはありません。一般的には数百円から数千円程度が目安とされていますが、大切なのは金額の多寡ではなく、故人を偲び、心から冥福を祈る気持ちです。包み方としては、白い無地の封筒に入れるか、袱紗に包むのが一般的です。表書きには「御仏前」や「御香典」と書きます。最近では、簡略化のため、お寺に用意されている封筒を使うことも多くなっています。どのような場合でも、丁寧に扱うことが大切です。
賽銭箱にお金を入れる際には、音を立てないように静かに入れるのが作法です。お焼香の前に入れるのか、読経の後に入れるのかなど、適切なタイミングは地域や宗派によって異なるため、周りの人に合わせて行うのが良いでしょう。迷った場合は、葬儀社の方に尋ねると丁寧に教えていただけます。
葬儀や法事における賽銭は、故人への感謝と追悼の気持ちを表す大切な行いです。金額の多寡ではなく、故人を偲び、心から冥福を祈る気持ちでお供えすることが大切です。賽銭を通じて、故人に思いを馳せ、安らかな眠りを祈る時間を持ちましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賽銭の意味 | 神仏への感謝の気持ちや願い、葬儀・法事では故人の成仏を願う気持ちを表す |
| 金額 | 決まりはなく、数百円~数千円程度が目安。金額より気持ちが大切 |
| 包み方 | 白い無地の封筒、袱紗、または寺にある封筒 |
| 表書き | 御仏前、御香典 |
| 賽銭を入れるタイミング | 地域や宗派によって異なるため、周りの人に合わせるのが適切 |
| その他 | 音を立てずに静かに入れる、丁寧に扱うことが大切 |
仏式と神式の違い

仏式と神式は、人の死後を弔う儀式ではありますが、その進め方や考え方には大きな違いがあります。まず、お布施の呼び方や包み方から見ていきましょう。仏式では「御仏前」として、白封筒、もしくは袱紗に包んでお供えします。袱紗を使う場合は、紫色のものが一般的です。一方、神式では「玉串料」として、白封筒に包んでお供えします。袱紗は使いません。
次に、お布施をお供えする場所とタイミングです。仏式では、焼香台の前に置かれた賽銭箱にお供えします。お供えするタイミングは、焼香の前後どちらでも構いません。神式では、玉串案に置かれた賽銭箱にお供えします。玉串案とは、神前に玉串を供えるための机のことです。お供えするタイミングは、玉串奉奠の前後です。玉串奉奠とは、榊の枝に紙垂をつけた玉串を神前に捧げる儀式のことです。
これらの違いは、それぞれの宗教が持つ死生観の違いに根差しています。仏式では、故人が仏様になることを願い、成仏を祈る儀式を行います。そのため、お布施は仏様への供え物という意味合いを持ちます。一方、神式では、故人が祖先神となり、子孫を見守ってくれる存在になると考えます。そのため、お布施は神様への感謝と、故人の霊を神様に託す際のお供え物という意味合いを持ちます。
このように、仏式と神式では、儀式の意味や作法が大きく異なるため、参列する際にはそれぞれの宗教の作法を理解し、失礼のないように振る舞うことが大切です。もし、作法が分からない場合は、葬儀社や寺院、神社の関係者に尋ねるのが良いでしょう。確かな知識を持って参列することで、故人を偲び、遺族を支えることができます。
| 項目 | 仏式 | 神式 |
|---|---|---|
| お布施の名称 | 御仏前 | 玉串料 |
| お布施の包み方 | 白封筒、もしくは紫色の袱紗に包む | 白封筒に包む(袱紗は使わない) |
| お布施をお供えする場所 | 焼香台の前の賽銭箱 | 玉串案に置かれた賽銭箱 |
| お布施をお供えするタイミング | 焼香の前後 | 玉串奉奠の前後 |
| 死生観 | 故人が仏様になることを願い、成仏を祈る | 故人が祖先神となり、子孫を見守る |
| お布施の意味合い | 仏様への供え物 | 神様への感謝と、故人の霊を神様に託す際のお供え物 |
お布施との違い
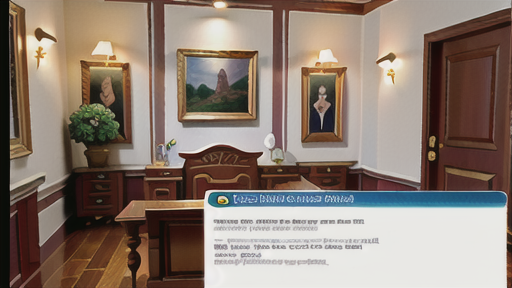
お賽銭とお布施。どちらも神仏にまつわる場面で金銭を納めますが、その意味合いと使い道は大きく異なります。お賽銭は、神社や寺院にお参りした際に、神仏への感謝の気持ちや願いを込めて納めるものです。金額に決まりはなく、少額でも問題ありません。賽銭箱に静かに落とすのが作法です。一方、お布施は、仏教の僧侶に対して、読経や戒名授与といった宗教行為への謝礼としてお渡しするものです。葬儀や法事など、僧侶にお世話になった際に必要となります。
お布施の金額は、地域や寺院の慣習、また法事の内容によって異なります。一般的には数万円から数十万円が相場とされていますが、事前に葬儀社や寺院に相談しておくと安心です。お布施は、白無地の封筒に入れ、「御布施」と表書きするのが一般的です。水引は使いません。葬儀社の方に渡してもらうか、お盆に載せてお渡しするのが良いでしょう。直接僧侶の手にお渡しするのは失礼にあたるとされていますので、避けましょう。
お布施を渡す時期は、葬儀の場合は葬儀が終わった後、法事の場合は法要の後になります。お布施は、僧侶の生活を支える大切な収入源です。感謝の気持ちとともに、丁重にお渡しすることが大切です。お賽銭は神仏への気持ちの表れ、お布施は僧侶への感謝の気持ちの表れです。それぞれの意味合いを理解し、状況に応じて適切に金銭を納めることで、故人を偲び、儀式を滞りなく執り行うことができます。
| 項目 | 意味合い | 金額 | 渡し方 | 渡す時期 |
|---|---|---|---|---|
| お賽銭 | 神仏への感謝の気持ちや願い | 少額で問題なし | 賽銭箱に静かに落とす | お参り時 |
| お布施 | 僧侶への謝礼 | 数万円〜数十万円(要相談) | 白無地の封筒に「御布施」と表書き、水引はなし。葬儀社経由、または盆に載せて渡す。直接手渡しはNG。 | 葬儀後、または法要後 |
マナーと心構え

葬儀や法事といった弔いの場への参列は、故人の霊を慰め、遺族の悲しみを分かち合う大切な機会です。その場にふさわしい服装や立ち居振る舞いを心がけ、故人や遺族に敬意を表すことが重要です。
まず服装に関しては、黒や濃紺、濃い灰色など落ち着いた色合いのものを選びましょう。光沢のある素材や華美な装飾は避け、慎ましい装いを心がけてください。アクセサリーも控えめなものにし、派手なものは身につけないようにしましょう。男性は黒のネクタイ、女性は黒のストッキングを着用するのが一般的です。
香典は、故人の霊前に供える金品であり、感謝と弔いの気持ちを伝える大切なものです。袱紗に包んで持参し、受付でふくさに包んだまま差し出し、両手で袱紗から出して渡します。表書きは薄墨の筆か筆ペンを用い、中袋には住所、氏名、金額を明記します。金額は故人との関係や自身の年齢、地域によって異なりますので、迷う場合は周りの人に相談してみましょう。
葬儀や法事は厳粛な場であることを忘れずに、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちを大切にしましょう。おしゃべりや携帯電話の使用は控え、静かに過ごしてください。会場では、係員の指示に従い、周りの人に配慮した行動を心がけましょう。焼香の作法や焼香の回数、数珠の持ち方など、地域や宗派によって作法が異なる場合があります。不明な点は、葬儀社や寺院、神社の関係者に尋ねるのが良いでしょう。
形式的な作法も大切ですが、何よりも大切なのは、故人を悼む気持ちです。故人との思い出を偲び、遺族の気持ちに寄り添い、温かい心で接することが大切です。葬儀や法事は、故人とお別れをし、遺族を支える場でもあります。参列を通して、故人の冥福を心から祈りましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 服装 | 黒、濃紺、濃い灰色など落ち着いた色合いの服装。光沢のある素材や華美な装飾は避け、アクセサリーも控えめにする。男性は黒のネクタイ、女性は黒のストッキングを着用。 |
| 香典 | 袱紗に包んで持参し、受付で袱紗から出して渡す。表書きは薄墨、中袋には住所、氏名、金額を明記。金額は故人との関係や自身の年齢、地域によって異なる。 |
| 会場での振る舞い | おしゃべりや携帯電話の使用は控え、静かに過ごす。係員の指示に従い、周りの人に配慮した行動を心がける。焼香の作法などは地域や宗派によって異なるため、不明な点は関係者に尋ねる。 |
| 心構え | 故人を悼む気持ちを大切に、故人との思い出を偲び、遺族の気持ちに寄り添う。葬儀や法事は故人とお別れをし、遺族を支える場。 |
最近の変化

近頃は、葬儀の形も大きく変わりつつあります。以前は、何日もかけて盛大な儀式を行うのが一般的でしたが、近年は、簡素ですぐに終わる葬儀を選ぶ方が増えています。時間も費用も抑えられることが選ばれる理由の一つでしょう。インターネットを使って、自宅にいながら葬儀に参列できるオンライン葬儀も登場し、遠くに住む親戚や仕事で忙しい人でも、故人に別れを告げられるようになりました。
お賽銭についても、時代の流れとともに変化が見られます。現金だけでなく、電子マネーやクレジットカードで支払える寺社も増えてきました。これは、現金を持ち歩かない人が増えたことや、感染症対策の一環として非接触型の支払方法が求められていることが背景にあります。また、香典に関しても、インターネットを通じて送金できるサービスが登場しており、利便性が向上しています。
こうした変化は、社会全体の変化を反映したものであり、今後ますます進んでいくと考えられます。しかし、昔から伝わるやり方を大切にする考え方も、依然として根強く残っています。葬儀や法事は、地域や宗派によって様々な慣習や作法があり、同じ地域でも家によって異なる場合もあります。参列する前に、どのようなしきたりがあるのかを調べておくことが大切です。それぞれの風習を重んじ、失礼のないように振る舞いましょう。
故人の好きだったことや、生前の希望を尊重することも重要です。葬儀や法事は、故人と最後のお別れをし、遺族を支える大切な機会です。形式にばかりこだわらず、故人を偲び、遺族を思いやる心を大切にしましょう。静かに故人の冥福を祈り、遺族とともに悲しみを分かち合うことが、葬儀や法事の本質と言えるでしょう。
| 項目 | 変化 |
|---|---|
| 葬儀 | 簡素化、オンライン化 |
| お賽銭 | 電子マネー、クレジットカード払い |
| 香典 | オンライン送金 |
| 参列 | 事前のしきたり確認 |
| 葬儀・法事 | 故人の好きだったこと、生前の希望、故人を偲び、遺族を思いやる心を尊重 |

