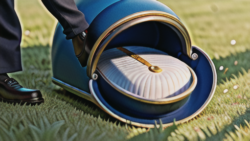法事
法事 六七日法要の基礎知識
六七日(むなのか、むなぬか)とは、人が亡くなってから四十九日目に行う仏教の法要のことです。四十九日は、亡くなった方の魂が次の世に生まれ変わる準備をする期間と考えられています。この期間は、中陰(ちゅういん)と呼ばれ、故人の霊は迷いの世界をさまよっているとされます。遺族は、故人の冥福を祈り、無事に次の世へ旅立てるように、七日ごとに法要を行います。初七日から始まり、二七日、三七日と続き、四七日、五七日、六七日、そして最後の七七日(四十九日)に至ります。六七日は、四十九日までの最後の法要にあたるため、特に重要な意味を持ちます。この日まで、遺族は故人のために祈り、供養を続けます。そして、六七日の法要をもって、故人の魂が成仏への道を歩み始めると信じられています。また、この日を境に、遺族も深い悲しみから少しずつ立ち直り、日常生活へと戻っていく大切な節目となります。六七日の法要では、僧侶にお経をあげてもらい、故人の霊を慰めます。そして、参列者と共に焼香を行い、故人に別れを告げます。法要後には、参列者で会食をすることが一般的です。これは、故人を偲び、共に過ごした時間を振り返る場であるとともに、遺族を支え、励ます意味もあります。地域によっては、この会食のことを「精進落とし」と呼ぶこともあります。六七日を過ぎると、喪明けとなり、遺族は日常生活に戻っていきますが、故人の冥福を祈る気持ちは忘れずに、今後も法要を営み、供養を続けていくことが大切です。