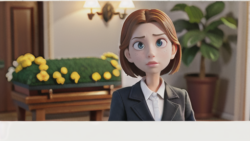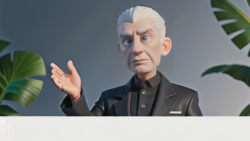葬式後
葬式後 神道における祖先崇拝:霊舎とは何か
神道において、霊舎はご先祖様の魂をお祀りする大切な場所です。仏教の仏壇と同じように、毎日お供え物をして祈りを捧げますが、その意味合いは大きく異なります。仏教では亡くなった方の魂の安らぎを願いますが、神道では亡くなった方は祖霊神となり、子孫を見守り、幸福へと導いてくださると考えられています。霊舎は、ご先祖様を偲び、その御加護に感謝を捧げる神聖な場所です。ご先祖様はいつも私たちと共にあり、見守ってくださっているという意識を持つことで、日々の暮らしに感謝の気持ちが生まれます。また、家族揃って霊舎に祈りを捧げることで、ご先祖様との繋がりを強め、家族の絆を深めることができます。霊舎には、ご先祖様の御霊を宿す霊璽(れいじ)と呼ばれるお札が安置されています。この霊璽は、神社で授与されるもので、大切に扱わなければなりません。霊璽の他に、お供え物として、米、塩、水、酒、榊などを供えます。毎日欠かさずお供えを新しいものに取り替え、清潔な状態を保つことが大切です。朝夕には、家族揃って霊舎の前に集まり、感謝の祈りを捧げます。霊舎は、単なる家具ではなく、家族の精神的な拠り所となる大切な場所です。ご先祖様への感謝の気持ちを忘れずに、日々大切に扱うことで、家庭に平和と繁栄をもたらすと信じられています。また、霊舎を通じてご先祖様と心を通わせることで、自身の心を清め、穏やかな気持ちで日々の生活を送ることができるでしょう。