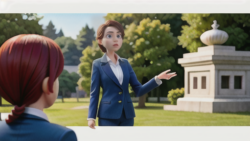相続・税金
相続・税金 お墓と消費税:知っておくべきこと
私たちの暮らしに身近な税金である消費税は、日々の買い物だけでなく、大きな買い物の際にも影響を及ぼします。特に高額な商品であるお墓は、消費税率の変化による影響が顕著に現れます。これまでにも何度か消費税率の引き上げがありましたが、2019年10月には8%から10%への引き上げが行われました。この2%の引き上げは、お墓の購入を考える人にとって大きな負担増となる可能性があります。お墓は、一度購入すれば何世代にもわたって使い続けられるものです。そのため、購入価格が高額になりがちです。消費税は価格に比例して課税されるため、高額なお墓の購入には、少なからず消費税の影響を受けます。例えば、100万円のお墓を購入する場合、8%の消費税率であれば8万円、10%になると10万円と、2万円もの差が生じます。200万円、300万円といった更に高額なお墓であれば、その差は更に大きくなります。お墓の購入は、人生における大きな買い物の一つです。子孫に負担をかけないためにも、消費税率の変化も考慮しながら、慎重に購入時期を検討する必要があります。少しでも負担を軽減するためには、消費税率が低い時期に購入することも一つの選択肢となります。しかし、お墓は価格だけで決めるべきものではありません。墓地の立地や環境、石材の種類、墓石のデザインなど、様々な要素を考慮して、自分にとって最適なお墓を選ぶことが大切です。消費税率のみにとらわれず、将来を見据えた上で、じっくりと検討を重ね、後悔のない選択をしましょう。