お墓の香立:種類と選び方

葬式を知りたい
先生、お墓参りに行った時、お線香をあげる場所の名前って何でしたっけ? 香炉みたいな名前だったと思うんですが…

お葬式専門家
ああ、それは香炉と香立のふたつがあるね。お線香を立てるタイプが香立、寝かせて焚くタイプが香炉だよ。最近は香炉の方が多いかな。

葬式を知りたい
じゃあ、お墓でよく見るのは香炉の方なんですね。どうして香立は少ないんですか?

お葬式専門家
そうだね。お墓は雨風が多いでしょう?香立だとお線香がすぐに消えちゃうから、屋根のない香立はあまり使われなくなったんだよ。最近は錆びにくいステンレス製の香炉が多いね。
香立とは。
お墓のすぐ前にあって、お線香をあげるための場所である『香立』について説明します。お線香を立てておくものは『香立』、寝かせておくものは『香炉』と呼びます。お墓は雨や風にさらされることが多いので、屋根がなくお線香が消えやすい『香立』を選ぶ人は少なくなってきました。最近は、さびにくいステンレス製の香立が一般的です。
香立とは
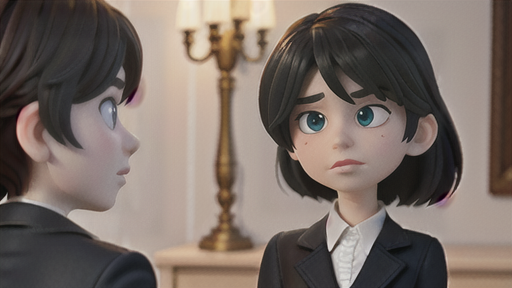
墓前に静かに線香の香りが漂う時、私たちは故人との繋がりを改めて感じます。その香りを届ける大切な役割を担うのが香立です。お墓の手前に置かれ、線香を焚いて香りを捧げるためのこの道具は、故人を偲ぶ気持ちを表す大切な存在です。
香立には大きく分けて二種類あります。一つは、線香を立てて使用する「香立」型です。細長い棒状の線香を立てるための穴が複数開いており、見た目もすっきりとしています。昔から使われてきた伝統的な形で、多くの墓地で見かけることができます。しかし、この形は屋外にあるお墓では、風雨にさらされやすいという欠点があります。風が強い日には線香が倒れたり、灰が飛び散ったりすることもあります。
もう一つは、線香を寝かせて使用する「香炉」型です。香炉の中には灰が敷き詰められており、その灰の上に線香を寝かせて焚きます。近年、こちらの香炉型が選ばれることが多くなっています。その理由の一つは、灰が飛び散りにくいことです。また、線香の火が風で消えにくいという利点もあります。さらに、一度にたくさんの線香を焚くことができるため、大人数でのお墓参りにも便利です。
どちらの香立も、故人を想う気持ちを表す大切な道具です。お墓参りの際には、どのような香立が設置されているかを確認し、それに合った方法で線香を焚きましょう。また、お墓の形状や周囲の環境に合わせて、適切な香立を選ぶことも大切です。それぞれの香立の特徴を理解し、故人に心を込めてお参りすることで、より深い祈りを捧げることができるでしょう。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 香立型 | 線香を立てて使用する | 見た目すっきり | 風で線香が倒れやすい 灰が飛び散りやすい |
| 香炉型 | 線香を寝かせて使用する 灰を敷き詰める |
灰が飛び散りにくい 線香の火が消えにくい 一度にたくさんの線香を焚ける |
香立の種類

お線香を焚く香立には、大きく分けて二つの種類があります。一つは棒状のお線香を立てて使う「立てるタイプ」、もう一つは寝かせて使う「寝かせるタイプ」です。
立てるタイプの香立は、その名の通り、お線香を垂直に立てて使います。お線香を立てるための穴が一つだけ開いているものや、複数のお線香を同時に立てられるように複数の穴が開いているものなど、様々な種類があります。このタイプの香立は、見た目もすっきりとしており、場所も取りません。しかし風の強い日などは、火が消えやすいという欠点もあります。お墓参りで使う際には、風の影響を受けにくい場所を選ぶ、風よけを使うなどの工夫が必要です。
一方、寝かせるタイプの香立は、お線香を横向きに寝かせて焚くタイプです。香炉のような形をしたものが多く、灰が飛び散りにくいという利点があります。また、風が吹いても火が消えにくいため、屋外でのお墓参りにも適しています。近年では、この寝かせるタイプの香立が主流となっています。
香立の素材も様々です。古くから使われている石や金属の他に、最近では錆びにくいステンレス製の香立も人気です。石の香立は重厚感があり、お墓の雰囲気にもよく馴染みます。金属製の香立は、洗練されたデザインのものも多く、様々な好みに対応できます。ステンレス製の香立は、錆びにくくお手入れが簡単なので、長く愛用することができます。
お墓の形状や環境、お好みに合わせて最適な香立を選びましょう。例えば、風の強い場所にあるお墓には、寝かせるタイプの香立がおすすめです。また、複数のお線香を同時に焚きたい場合は、立てるタイプで複数の穴が開いているものを選ぶと良いでしょう。
| 種類 | 使い方 | メリット | デメリット | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 立てるタイプ | お線香を垂直に立てる | 見た目すっきり、場所を取らない | 風が強いと火が消えやすい | 複数の穴が開いているものもある |
| 寝かせるタイプ | お線香を横向きに寝かせる | 灰が飛び散りにくい、風が吹いても火が消えにくい | – | 近年主流、香炉のような形のものが多い |
| 素材 | 特徴 |
|---|---|
| 石 | 重厚感、お墓の雰囲気に馴染む |
| 金属 | 洗練されたデザインが多い |
| ステンレス | 錆びにくい、お手入れ簡単 |
香炉の選び方

香炉はお墓参りの際に欠かせない大切な道具であり、故人に想いを届けるための大切な役割を担っています。香炉を選ぶ際には、いくつかの点に注意することで、よりふさわしい一品を見つけることができるでしょう。
まず、お墓全体の雰囲気との調和を考えてみましょう。お墓の建立年代や様式、そして使われている石材の色や質感と、香炉の素材やデザインが合っていることが大切です。例えば、古くからある和型のお墓で、黒や灰色の石が用いられている場合には、落ち着いた色合いの石材や、柔らかな風合いの陶器の香炉が似合うでしょう。一方、近代的な洋型のお墓で、白やベージュの石が用いられている場合は、光沢のある金属製の香炉が調和するかもしれません。
香炉の大きさも重要な要素です。小さすぎる香炉ではお線香を十分に焚くことができず、灰がこぼれてしまうかもしれません。反対に、大きすぎる香炉は見た目にも不釣り合いで、お墓全体のバランスを崩してしまう可能性があります。お墓の広さや、普段のお参りの人数を考慮して、適切な大きさの香炉を選びましょう。
素材にもこだわってみましょう。石材は耐久性に優れ、風雨にさらされても劣化しにくいという利点があります。陶器は、素朴で温かみのある雰囲気が魅力です。金属は洗練された印象を与え、お手入れもしやすいでしょう。それぞれの特徴を理解し、お墓の雰囲気や好みに合わせて選びましょう。
近年は、伝統的なデザインだけでなく、様々な形や模様の香炉が販売されています。故人が生前好きだった花や、趣味に関するモチーフが施された香炉を選ぶことで、故人を偲ぶ気持ちを表すこともできるでしょう。故人の人となりや好みに合った香炉を選ぶことは、お墓参りをより meaningful なものにしてくれるはずです。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| お墓全体の雰囲気との調和 | お墓の様式、石材の色や質感と香炉の素材やデザインを合わせる。和型墓石には落ち着いた色合いの石材や陶器、洋型墓石には光沢のある金属製などが合う。 |
| 香炉の大きさ | お墓の広さや参拝人数に合った適切な大きさを選ぶ。小さすぎるとお線香が焚きにくく、大きすぎると不釣り合いになる。 |
| 素材 | 石材は耐久性、陶器は温かみ、金属は洗練さが特徴。それぞれの特性を理解し、好みに合わせて選ぶ。 |
| 故人の人となりや好みに合った香炉を選ぶ | 故人が好きだった花や趣味のモチーフなど、故人を偲ぶ気持ちを表す香炉を選ぶことで、お墓参りをより meaningful なものにする。 |
香立の素材

お墓にお線香を供える際に欠かせない香炉。その土台となる香立は、素材によって見た目や耐久性が大きく変わります。お墓の雰囲気を壊さず、長くお使いいただくためには、素材の特徴を良く理解して選ぶことが大切です。
まず、古くから使われている石材製の香立は、重厚感があり、風雨にさらされてもびくともしない丈夫さが魅力です。落ち着きのある風格が、お墓の雰囲気を引き締めます。代表的な素材である御影石は、硬くて緻密なため、長年の使用に耐えることができます。しかし、経年劣化により、表面にひび割れが生じる可能性があることも考慮に入れておきましょう。定期的なお手入れで美しさを保つことができます。
次に、金属製の香立を見てみましょう。洗練された見た目で、現代的なお墓にもよく合います。素材としては、錆びにくいステンレスが主流です。真鍮など他の金属に比べ、お手入れの手間が少なく、長く美しさを保つことができます。また、様々なデザインが available なので、お墓の雰囲気に合わせて選ぶ楽しさもあります。
最後に、陶器製の香立は、柔らかな風合いが特徴です。和風の落ち着いた雰囲気のお墓によく馴染みます。素朴で温かみのある見た目で、故人を偲ぶ場にふさわしい穏やかな印象を与えます。ただし、石材に比べると衝撃に弱いため、取り扱いには注意が必要です。
このように、それぞれの素材にはメリットとデメリットがあります。例えば、海に近い場所に設置されたお墓では、潮風による錆を防ぐため、ステンレス製の香立が適しています。また、伝統的な雰囲気を重視するのであれば、石材製の香立がおすすめです。お墓の環境や好みに合わせて、最適な素材を選びましょう。お墓参りの度に使うものだからこそ、香立選びにも心を込めて、故人を偲ぶ場を大切にしたいものです。
| 素材 | メリット | デメリット | 適した環境 |
|---|---|---|---|
| 石材 | 重厚感、丈夫、長持ち | 経年劣化によるひび割れ | 伝統的な雰囲気のお墓 |
| 金属 (ステンレス) |
洗練された見た目、錆びにくい、お手入れ簡単 | – | 現代的なお墓、海に近い場所 |
| 陶器 | 柔らかな風合い、和風の雰囲気 | 衝撃に弱い | 和風の落ち着いた雰囲気のお墓 |
香立の手入れ

お墓参りの際に欠かせない香炉。その土台である香立は、常に風雨にさらされ汚れやすく、定期的にお手入れをすることで美しさを保ち、長く使うことができます。お線香の灰や燃え残りは、お参りのたびにこまめに取り除きましょう。香炉の中に灰がたまると、湿気を帯びやすく、香炉や香立の劣化を早める原因となります。お参りの際には、香炉の灰を専用の灰ふるいなどを使って取り除き、柔らかい布で丁寧に汚れを拭き取ってください。灰や汚れを放置すると、香炉にこびりつき、落ちにくくなってしまいます。
香立の材質によって適切なお手入れ方法は異なります。金属製の香立は、雨風にさらされると錆が発生しやすいため、乾いた布で水気を拭き取り、定期的に防錆剤を塗布することをお勧めします。防錆剤は、ホームセンターなどで手軽に購入できます。石材の香立は、風雨による風化を防ぐために、石材専用の保護剤を使用すると良いでしょう。保護剤を塗布することで、石材の表面を保護し、劣化を防ぎます。また、苔やカビが発生した場合には、柔らかいブラシを使って丁寧に落としましょう。研磨剤の入った洗剤を使用すると、石材に傷をつける可能性がありますので、使用は避けましょう。
香立を長く美しく保つためには、こまめなお手入れが大切です。お墓参りの際に、香炉の灰を取り除き、香立の汚れを拭き取る習慣をつけ、材質に合わせた適切な方法でお手入れをすることで、故人を偲ぶ大切な場所を美しく保ち続けましょう。
| お手入れ対象 | 日常のお手入れ | 材質別のお手入れ |
|---|---|---|
| 香炉 |
|
|
| 香立(金属製) |
|
|
| 香立(石材) |
|
まとめ
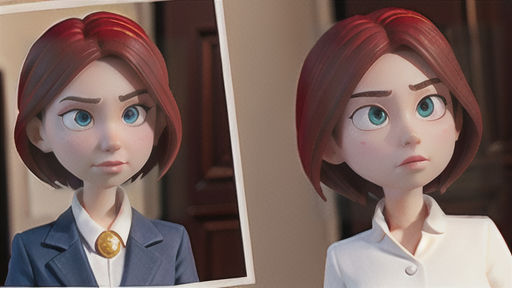
お墓参りに欠かせない道具の一つに、故人に想いを伝える大切な役割を持つ香立があります。香を焚くためのこの小さな道具にも、様々な種類や素材、お手入れ方法があり、それらを理解することで、より良いお墓参りを行うことができます。
近年では、香炉型の香立が主流となっています。これは、お線香を寝かせて焚くことができるため、風などの影響を受けにくく、お線香が途中で消えてしまう心配が少なくなります。また、灰の飛び散りを抑える効果もあり、お墓の周囲を清潔に保つことができます。従来の、線香を立てるタイプの香立では、風の強い日などは線香が倒れてしまうこともありましたが、香炉型であればそのような心配もありません。さらに、灰が飛び散りにくいので、お掃除の手間も軽減されます。
香炉型の香立以外にも、様々な形状や材質のものが存在します。例えば、陶磁器や金属、石材など、素材によって見た目や耐久性が異なります。お墓のデザインや雰囲気に合わせて、相性の良い香立を選ぶことで、お墓全体の調和がとれ、より落ち着いた空間を演出することができます。また、故人の好きだった色や形を考慮して選ぶことも、故人を偲ぶ大切な時間を作る上で良いでしょう。
香立を長く美しく保つためには、定期的なお手入れも重要です。お墓参りの際に、香立の状態を確認し、灰や汚れを取り除きましょう。柔らかい布で優しく拭き取ったり、水洗いをすることで、美しい状態を保つことができます。特に金属製の香立は、錆が発生しやすいので、こまめな手入れが必要です。また、破損している場合は、修理または交換を検討しましょう。
香立は、単なる道具ではなく、故人への想いを伝える大切な橋渡しです。適切な香立を選び、丁寧にお手入れをすることで、心静かにお墓参りをし、故人を偲ぶ時間を大切にしましょう。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | お手入れ |
|---|---|---|---|---|
| 香炉型 | お線香を寝かせて焚く | 風で消えにくい、灰が飛び散りにくい、掃除の手間が軽減 | – | 灰や汚れを取り除き、柔らかい布で拭き取ったり、水洗いをする。 |
| 線香を立てるタイプ | 従来のタイプ | – | 風の強い日に線香が倒れることがある。 | 灰や汚れを取り除き、柔らかい布で拭き取ったり、水洗いをする。 |
| その他(陶磁器、金属、石材など) | 素材によって見た目や耐久性が異なる | お墓のデザインや雰囲気、故人の好みに合わせて選べる | 金属製は錆びやすい | 灰や汚れを取り除き、柔らかい布で拭き取ったり、水洗いをする。金属製はこまめな手入れが必要。破損時は修理または交換。 |

