御会式について

葬式を知りたい
先生、『御会式』って言葉は葬式とか法事の時に使うんですよね?どんな時に使うんですか?

お葬式専門家
いい質問だね。『御会式』は葬式や法事とは少し違うんだよ。日蓮聖人の亡くなった日をしのぶ法要のことなんだ。毎年10月12日と13日に行われるんだよ。

葬式を知りたい
じゃあ、お葬式とかお坊さんがお経を読むのとは違うんですか?

お葬式専門家
そうだね。お葬式は故人のために行うものだけど、『御会式』は日蓮聖人の教えを偲び、感謝する法要なんだ。身延山久遠寺をはじめ、全国の日蓮宗のお寺で盛大に行われているんだよ。
御会式とは。
日蓮聖人の命日である10月12日と13日に行われる法要である『お会式』について説明します。この法要は、日蓮宗の総本山である身延山久遠寺をはじめ、全国各地の日蓮宗のお寺で盛大に行われています。
御会式の由来

御会式とは、日蓮聖人が亡くなられた10月13日を中心に行われる、日蓮宗における最も大切な法要です。日蓮聖人は弘安五年(1282年)10月13日、池上宗仲という方の屋敷で61歳の生涯を閉じられました。そのお亡くなりになったことを深く悲しむ弟子たちによって、翌年から聖人を偲ぶ法要が営まれるようになりました。これが御会式の始まりと伝えられています。
御会式という言葉は、もともとサンスクリット語のウパニシャッドを漢字で書き表した会式という言葉に、尊敬の気持ちを込めた「御」を付けたものです。ウパニシャッドとは古代インドの聖典であり、会式という言葉は元々は仏教の教えを説く集まりのことを指していました。しかし、日蓮聖人がお亡くなりになった後、その霊を慰め、功績をたたえる法要を指す言葉として使われるようになりました。
鎌倉時代、御会式は、日蓮聖人が最期を過ごした池上邸や、お墓がある池上妙本寺を中心に行われていました。その後、時代が進むにつれて、次第に全国の日蓮宗のお寺で盛大に営まれるようになりました。現在では、各地で万灯練供養など様々な行事が行われ、多くの人々が日蓮聖人の教えに思いを馳せる大切な機会となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 御会式 |
| 意味 | 日蓮聖人の命日(10月13日)を中心に行われる、日蓮宗で最も重要な法要 |
| 由来 | 日蓮聖人の死後、弟子たちが聖人を偲び、翌年から法要を始めたのが始まり。 |
| 語源 | サンスクリット語のウパニシャッド(会式)に尊敬の「御」を付けたもの。元は仏教の教えを説く集まりを指していたが、のちに日蓮聖人の功績をたたえる法要を指すようになった。 |
| 歴史 | 鎌倉時代は池上邸や池上妙本寺を中心に行われていたが、時代と共に全国に広まった。 |
| 現在 | 各地で万灯練供養など様々な行事が行われている。 |
御会式の特徴

御会式とは、日蓮聖人のご命日である10月13日を中心に行われる、日蓮宗の一大法要です。その最大の特徴は、万灯練り供養と呼ばれる、日蓮聖人を偲び、たくさんの灯明を掲げて行う行列です。この万灯練り供養は、日蓮聖人が亡くなられた際に、弟子たちが提灯を掲げて駆けつけたという故事に由来しています。
提灯の灯りは、人々を迷いの暗闇から救い出す、日蓮聖人の教えを広める「灯明」の象徴です。参列者は、それぞれの想いを胸に、日蓮聖人の教えを後世に伝える決意を新たにしながら、読経を唱え、街を練り歩きます。
御会式では、万灯練り供養以外にも、読経や唱題、日蓮聖人の教えを説く法話などが行われます。また、日蓮聖人の生涯を描いた絵巻物や、日蓮聖人にまつわる貴重な品々を展示する寺院もあります。
地域によっては、伝統芸能が奉納されたり、たくさんの屋台が並び、地域をあげて盛大に執り行われます。特に、日蓮聖人が晩年を過ごした身延山久遠寺で行われる御会式は、全国から多くの参拝者が訪れ、大変な賑わいを見せます。
このように、御会式は、日蓮聖人の教えに触れ、その功績を偲ぶ神聖な儀式であると同時に、地域の人々にとっても大切な行事として、今日まで受け継がれているのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 御会式とは | 日蓮聖人のご命日である10月13日を中心に行われる、日蓮宗の一大法要 |
| 最大の特徴 | 万灯練り供養(日蓮聖人を偲び、たくさんの灯明を掲げて行う行列) |
| 万灯練り供養の由来 | 日蓮聖人が亡くなられた際に、弟子たちが提灯を掲げて駆けつけたという故事 |
| 提灯の灯りの意味 | 人々を迷いの暗闇から救い出す、日蓮聖人の教えを広める「灯明」の象徴 |
| 御会式で行われること | 読経、唱題、法話、(地域によっては伝統芸能の奉納、屋台の出店など) |
| 代表的な御会式 | 身延山久遠寺(日蓮聖人が晩年を過ごした場所) |
| 御会式の意義 | 日蓮聖人の教えに触れ、その功績を偲ぶ神聖な儀式であり、地域の人々にとっても大切な行事 |
御会式の時期

日蓮聖人のご命日である10月13日を中心として営まれる御会式。この大切な法要は、各地のお寺で様々な形で執り行われています。多くの場合、12日の夜から13日の未明にかけて、厳かな法要が営まれます。特に、夜を彩る万灯練り供養は、荘厳な雰囲気の中で行われ、多くの人々の心を引きつけます。
中でも、日蓮聖人の総本山である身延山久遠寺では、10月11日から13日までの3日間、大規模な法要が執り行われます。全国から多くの参拝者が集まり、聖人のご遺徳を偲び、祈りを捧げます。読経の声が山々に響き渡り、荘厳な雰囲気に包まれます。
10月13日以外にも、地域によっては、日蓮聖人にゆかりのある日を選んで御会式を営むところもあります。例えば、日蓮聖人が佐渡に流刑されたことを偲ぶ「佐渡御会式」。この御会式は、厳しい流刑の生活を送られた聖人のご苦労を偲び、その教えに思いを馳せる機会となっています。また、鎌倉に帰還されたことを祝う「お帰り御会式」も各地で行われています。日蓮聖人が鎌倉に戻られた喜びを分かち合い、教えが広く伝わるようにと願いを込めたお祭りです。
このように、御会式は、日蓮聖人のご命日を偲ぶだけでなく、その教えに触れ、信仰を深める大切な機会となっています。それぞれの地域で、様々な形で執り行われる御会式は、人々の心に温かい光を灯し続けています。
| 名称 | 日付 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 御会式(一般的な例) | 10月12日夜〜13日未明 | 各地の寺院 | 厳かな法要、万灯練り供養 |
| 身延山久遠寺の御会式 | 10月11日〜13日 | 身延山久遠寺 | 大規模な法要 |
| 佐渡御会式 | 日蓮聖人にゆかりのある日 | 佐渡 | 日蓮聖人の佐渡流刑を偲ぶ |
| お帰り御会式 | 日蓮聖人にゆかりのある日 | 各地 | 日蓮聖人の鎌倉帰還を祝う |
参列の方法
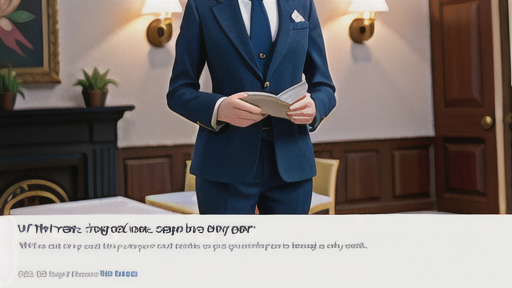
お会式への参列に際し、服装に関する厳密な決まりはありません。普段着で問題ありませんが、華美な服装は避け、落ち着いた色合いで慎み深い装いを心がけましょう。お会式は、日蓮聖人のご遺徳を偲ぶ厳粛な儀式です。派手な服装は場違いな印象を与えてしまうかもしれません。特に、黒や紺、グレーなど落ち着いた色味の服装が好ましいでしょう。また、アクセサリーも控えめにするのが適切です。
寺院によっては参拝料が必要な場合がありますので、事前に確認しておきましょう。お寺に問い合わせるか、ウェブサイトで確認するのが確実です。参拝料は、お寺の維持管理や法要の運営に充てられます。お気持ちがあれば、少し多めに納めることもできます。
お会式では読経や唱題が行われます。静かに参列し、周りの方に迷惑をかけないように配慮しましょう。携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定しておきましょう。また、おしゃべりや私語は慎み、厳粛な雰囲気を保つことが大切です。小さなお子様連れの場合は、ぐずったり騒いだりしないよう注意が必要です。
万灯練り供養に参加する場合は、係員や寺院関係者の指示に従って行動しましょう。万灯練り供養は、日蓮聖人にゆかりのある提灯を掲げて練り歩く儀式です。提灯の持ち方や歩き方など、指示に従って安全に参列することが重要です。
お会式では、日蓮聖人にまつわる様々な催し物が行われることがあります。事前に寺院のウェブサイトや掲示などで情報を確認しておくと、より深くお会式を楽しむことができるでしょう。例えば、法要の他に、日蓮聖人の生涯を描いた絵巻物の展示や、日蓮宗にまつわる講演会などが開催される場合もあります。
お会式は、日蓮聖人の教えに触れ、そのご遺徳を偲ぶ貴重な機会です。ぜひ、お近くの寺院でお会式に参列し、心静かなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 服装 | 落ち着いた色合いで慎み深い装い(黒、紺、グレーなど)。華美な服装やアクセサリーは避ける。 |
| 参拝料 | 寺院により異なる。事前に確認し、お気持ちがあれば多めに納めることも可能。 |
| 参列時のマナー | 静かに参列し、携帯電話の電源を切るかマナーモードにする。私語は慎み、子供連れの場合は注意する。 |
| 万灯練り供養 | 係員や寺院関係者の指示に従って行動する。 |
| 催し物 | 寺院によって異なる。事前にウェブサイトなどで確認するとより楽しめる。 |
まとめ

日蓮聖人のご命日である十月十三日には、全国各地の日蓮宗寺院で『御会式(おえしき)』と呼ばれる重要な法要が営まれます。これは、日蓮聖人が亡くなられた日を悼(いた)むと共に、その尊い教えを後世に伝えるために行われる大切な儀式です。御会式は、単なる追悼の儀式ではなく、日蓮聖人の教えを学び、その遺徳を偲び、信仰を新たにするための貴重な機会となっています。
御会式の中でも特に有名な行事は『万灯練り供養』です。これは、日蓮聖人の入滅を象徴する提灯を掲げ、街中を練り歩くものです。多くの信者が唱題を唱えながら行列に加わり、厳粛な雰囲気の中にも活気に満ち溢れています。万灯の灯りは、日蓮聖人の教えが暗闇を照らす希望の光であることを象徴しており、見る者の心に深い感動を与えます。
また、御会式では、法要や読経の他、地域によっては、稚児行列や演奏、露店などが並ぶ催し物も行われます。これらは、地域の人々にとって楽しみな秋の行事として親しまれており、地域コミュニティの活性化にも貢献しています。御会式は、宗教的な儀式であると同時に、地域の文化行事としての側面も持っていると言えるでしょう。
時代と共に、その形式や内容は少しずつ変化を遂げてきていますが、日蓮聖人の教えを伝え、遺徳を偲ぶという本質は、今も昔も変わらず脈々と受け継がれています。そして、これからも多くの人々に希望と勇気を与え続け、心の支えとなることでしょう。日蓮聖人の教えに触れ、その生涯に思いを馳せる機会として、ぜひ一度、お近くの寺院で開催される御会式に参列してみてください。きっと、心に残る貴重な体験となるはずです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 御会式(おえしき) | 日蓮聖人のご命日(10月13日)に全国各地の日蓮宗寺院で行われる重要な法要。日蓮聖人の死を悼み、教えを後世に伝える。教えを学び、遺徳を偲び、信仰を新たにする機会。 |
| 万灯練り供養 | 日蓮聖人の入滅を象徴する提灯を掲げ、街中を練り歩く。日蓮聖人の教えが暗闇を照らす希望の光を象徴。 |
| その他催し物 | 法要、読経、稚児行列、演奏、露店など。地域の文化行事としての側面も持つ。 |
| 本質 | 日蓮聖人の教えを伝え、遺徳を偲ぶという本質は、今も昔も変わらず受け継がれている。 |

