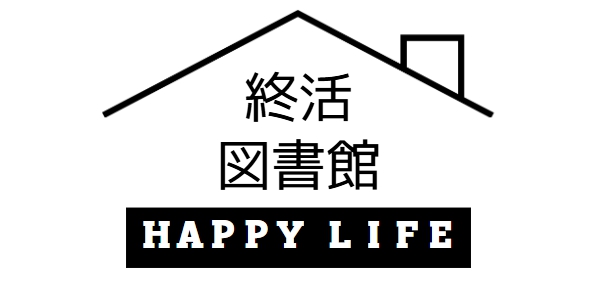相続・税金
相続・税金 遺留分減殺請求とは?
人が亡くなり、形見分けとして財産が残される時、その分け方は故人の遺言で決められます。しかし、遺言の内容によっては、残された家族にとってあまりに不公平な場合もあります。そのような時に、法律によって最低限保障されている相続分があり、これを取り戻せる権利があります。これを「遺留分減殺請求」と言います。この制度は、遺言によって不当に低い遺産しか受け取れない相続人を守るためのものです。例えば、故人が生前に特定の人物だけに財産を譲るといった遺言を残した場合、残された配偶者や子どもたちは生活に困窮する可能性があります。このような事態を防ぐために、法律は一定の割合の遺産を相続人に保障しています。これが遺留分と呼ばれるものです。遺留分は、配偶者や子どもであれば遺産の半分、父母であれば遺産の3分の1と法律で定められています。もし、遺言によってこれらの割合を下回る遺産しか受け取れない場合、不足分を請求することができます。これが遺留分減殺請求です。ただし、遺留分減殺請求は故人の意思を完全に無視するものではありません。故人には自分の財産を自由に処分する権利があります。遺留分減殺請求は、その権利と、残された家族の生活を守る権利とのバランスをとるための制度です。この制度を正しく理解することは、相続に関する揉め事を避ける上でとても大切です。故人の最期の思いを尊重しつつ、残された家族が安心して生活できるよう、この制度を有効に活用することが重要です。